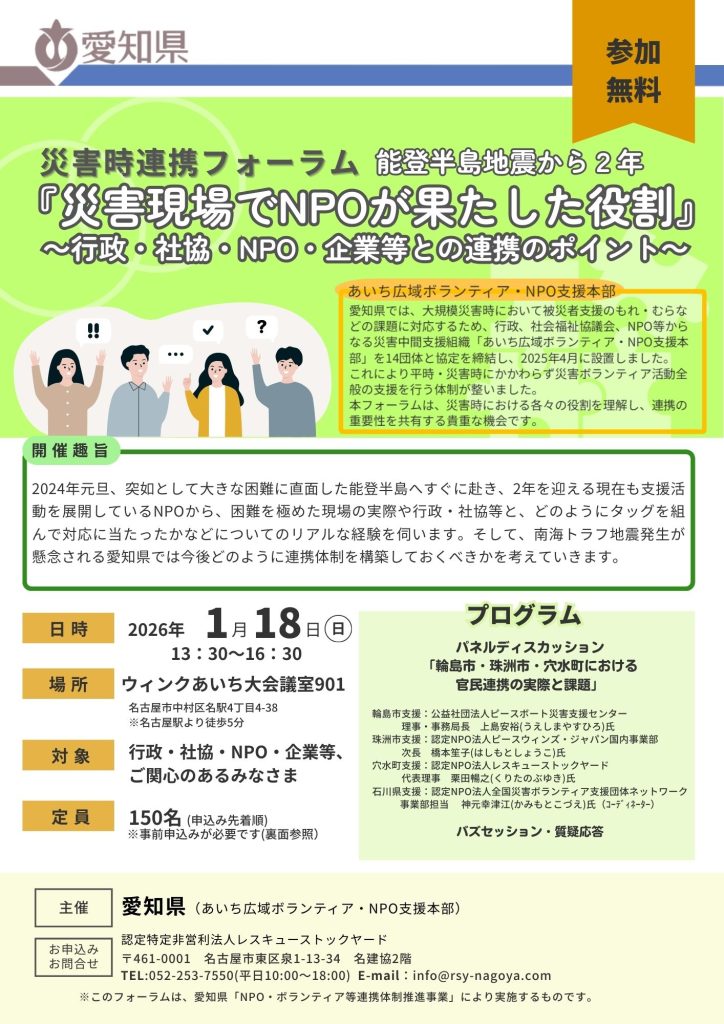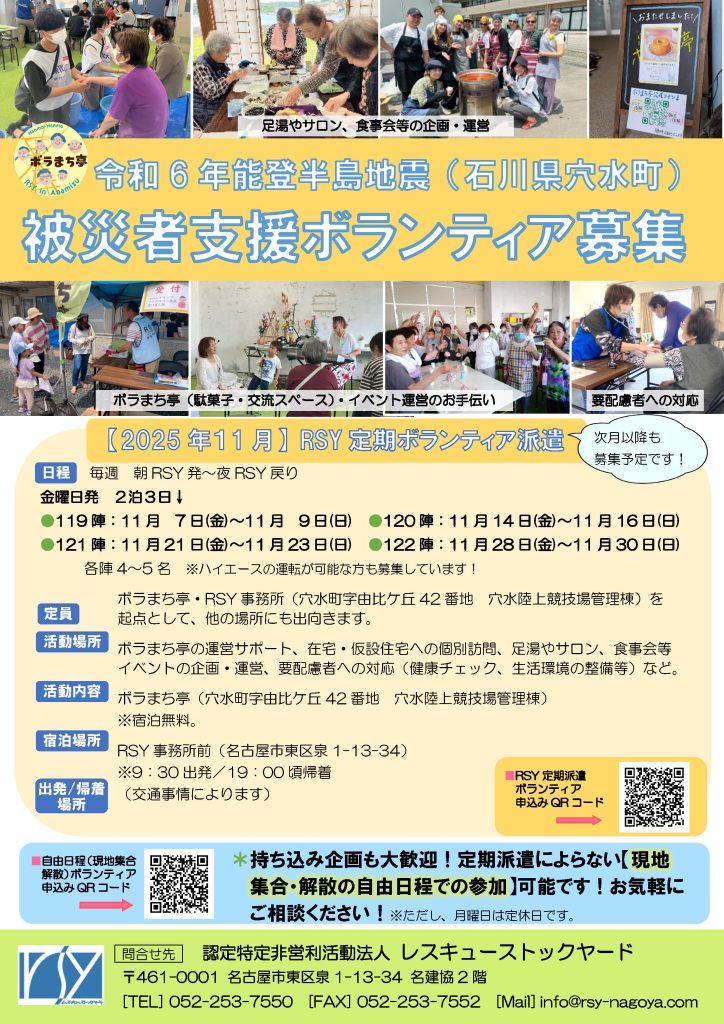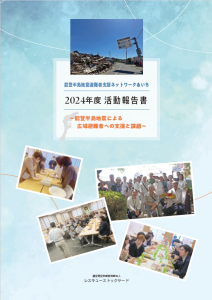みなさま
お世話になります。RSY事務局です。
3月11日(火)~12日(水)に実施した七ヶ浜スタディツアーについてご報告させていただきます。今回は、大学院生や大学関係者、防災・災害ボランティア、会社員など、20~70代の参加者7名とRSYスタッフ3名の合計10名で七ヶ浜を訪れました。
1日目は、七ヶ浜に到着後、きずなハウス(みんなの家)で開催されていた「七ヶ浜町震災の記憶展」を見学しました。その後、七ヶ浜町公園墓地「蓮沼苑」の東日本大震災慰霊碑前で執り行われた追悼式に参列し、14:46に黙とうを捧げ、献花を行いました。
16時からは、七ヶ浜町中央公民館にて「町民&ボランティア交流会」を実施しました。七ヶ浜の若者たちによる震災伝承団体「きずなFプロジェクト」、元RSY七ヶ浜スタッフの石木田さんが代表を務める「地球子屋(てらこや)」の活動紹介の後、3グループに分かれて5名の七ヶ浜住民の方々と交流を行いました。震災当時の避難行動や避難所生活、仮設住宅での生活などについて、どのような困難があり、どう乗り越えてこられたか、今後の災害に向けてどんな備えが必要かなど、それぞれの体験からのお話しをしていただきました。





2日目は、七ヶ浜町巡回語り部ツアー(フィールドワーク)として、石木田さんのガイドで、松島湾を眺められる多聞山、代ヶ崎浜の防潮堤に作られたおはじきアート、吉田浜の眺望台、復興整備事業で開発された花渕浜多目的広場や菖蒲田浜ながすか多目的広場、笹山地区の高台住宅団地、菖蒲田海岸防潮堤などを巡りました。
その後、小学2年生で被災し、現在は語り部として震災の伝承活動に関わるNPOの職員となった若生遥斗さんのガイドで、震災当時在籍していた汐見小学校から、実際に避難をした弥栄神社の高台までの避難ルートを歩き、当時の状況や今の想いをお聞きしました。





■参加者の皆さんからの感想
〇昨年に引き続き2度目の訪問でしたが、町内を巡りながらの見学は初めてでした。町内には3.11の津波に関する表示が沢山ありました。ここまで津波が到達したのかと何度も驚かされ、被災直後の写真に胸が締めつけられました。しかしそれだけ甚大な被害を受けた中でも、住民の皆さんが七ヶ浜の海を心の底から大切に思っているということが、今回のツアーで最も印象に残ったことです。震災当時、できることはなんでもやっていたというお話から、現実を受け止め、今後も海と共に生きていく覚悟を感じました。辛い時間が長く続いたはずなのに、今は強さすら感じさせるみなさんの姿は、まだ自分に不足する覚悟を見直させてくださいました。発災後、周囲と連携できるよう普段からコミュニティを大切にすること、個々に合った非常用持ち出し袋を準備し適切な場所に保管すること、多めに食料や水を備蓄することなど、今できる準備はたくさんあると感じました。

〇14年前の3月11日、中学2年生だった私は、校外学習をしていました。教室に戻ると先生が走って来て「今、日本が大変なことになっています。これをみて気分が悪くなる人もいるかもしれない。でもこれを志摩市に住む自分たちが経験する番だっかもしれない。この映像を自分たちは見なければいけない。」と話し、津波の生放送を見せてくれました。あの日からテレビの中の現実で何が起こっていたのか、14年経ってしまったけれどやっと学びにいくことができました。
今回、1番心に残ったのは、「地震の揺れに耐えてから、それからが本当の震災だった。」という言葉です。これは高台にある避難所で100日間、一度も自宅に戻らず避難所の運営、支援に当たった被災者の方からお聞きしました。避難所では高齢者など要支援者の対応やケアを寝る間を惜しんで行ったそうです。外部支援者ではなく、普段を知っている地元の人だからこそ行えるより細やかなケアがあると思います。しかしその負担は計り知れません。普段から災害時を想定した訓練と想定をしておくことが、被災者となった時の自分や地域の人々の支えとなることを改めて感じました。


〇今回は講演、フィールドワークとフル回転して頂いた石木田裕子さんにずっとお世話になりました。その中で地球小屋「てらこや」が印象的でした。地域の交流施設として毎月第2土曜日、「みんなの家」「きずな公園」に集まり、お弁当持参で1日過ごすアイデアはいいですね。その中で震災の伝承、震災遺構の見学、防災学習としてなまず学校、防災食のカレーつくり、外部とコラボで紙コップロケットつくり、小学生の食育、キッズ企画と多岐多彩のわたる活動から石木田さんの熱い思いと多様性に感心させられました。前期高齢者とお聞きしましたが、やれることは何でもやるという姿勢に満ち溢れ、今後のさらなる活躍が期待したいと思いました。
名古屋でも既成概念にとらわれず、子どもたちや若者の力とアイデアを引き出して、自らもやっていける取り組みをしていきたいと思いました。それはきずなFプロジェクトの活動をお聞きしさらに強く感じました。
最後にフィールドワークのおはじきアートが心に残っています。物語があり、松島を背景のあるのがいいですね。またこれからも訪問したくなりました。


〇想像よりスケジュールに余裕があり、内容も多岐にわたりメリハリがあって非常に良かった。特に汐見小学校から裏山の避難経路を実際に歩いたのは印象に残りました。
個人的な反省になるのですが、ボランティアに肩書きとかはあまり関係ないと思いつつも、穴水に行かれている方や地元のボランティア団体に所属されている方ばかりでちょっと気後れしていました。また、久しぶりに初見の被災者の方と話したので、距離感とか踏み込み具合など考えすぎて聞く一方になってしまいました。この反省を生かしつつ、15周年のツアー?企画?も日程が合えば参加したいと思います。

〇ツアーでお聴きした話の中で、穴水町と七ヶ浜が繋がっていたことに驚きました。共助とは人が人を助け繋がることも大切なことですが、地域と地域の繋がる事も大切な事だと、目からウロコでした。
ワークグループでは、きずなFプロジェクトの皆さんの若さに驚くとともにシッカリとした「伝え」を子供たちに広げている活動内容のもさらに感心させられました。若者独特な発想でさらなる活動に期待しています。伊丹さんからは「南海トラフ地震での被害は都市型なので想像がつかないけれど、郡部では七ヶ浜に似た地域もある。被災者として発信していくので東海地域でも広げて欲しい」との意見に、自分の地域で七ヶ浜の発信をどう広げていくかが大切な事だと痛感させられました。
石木田さんの案内での七ヶ浜巡回語り部ツアーでは、石木田さんのパワフルさにも驚きましたが、14年の時の流れにも驚きました。最後に若生くんの七ヶ浜語り部デビューに参加さしていただいたことは大変光栄に思います。災害を風化させないためにも頑張っていただきたい。毎年行われている七ヶ浜ツアー、長く続くようお願いします。


〇3月11日~12日の2日間、初めて七ヶ浜に行きました。1日目は震災の記憶展見学、慰霊塔参拝、住民の皆さんと交流会。2日目は七ヶ浜町巡回語り部ツアー。交流会でIさん御夫妻からお話を伺いました。ご苦労もされ、大変だった事から次に伝える話です。
①被災してもう一度家に引き返した人が犠牲になった
②(震災の)2日前に地震があり、皆で集合場所を決めていた
③避難所ではみんなが家族。当番、役割を決めた
④困り事、要求は行政に伝える
⑤眠れない、食べれない、精神的にも体調不良になる
南海トラフ地震が懸念される中で、このことをどう伝えていくか、改めて考える機会になりとても勉強になりました。