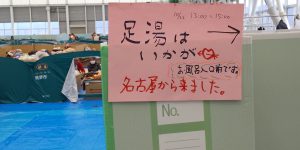みなさま
お世話になります。RSY事務局です。
先日1月17日で、阪神・淡路大震災から25年が経ちました。RSYでは毎年、法人設立以前より繋がりをもたせて頂いているKOBE(※)の方々を訪問しています。今年もスタッフ含め15名のツアー参加者の皆さんと共に、震災から25年目を振り返り、活動の原点に立ち返る機会となりました。
※「 KOBE 」神戸市のことではなく、阪神・淡路大震災大震災の被災者や被災地すべてを指す総称として用いています。
以下、ツアー当日のレポートです。
――――――――――――――――――――
現地の方々との交流
――――――――――――――――――――
★被災地NGO協働センター
毎年、地震発生時刻の1月17日午前5時46分は、被災地NGO協働センターの追悼式に参加しています。今回も参加者一同、黙とうを捧げ、僧侶でもあるRSY代表理事・栗田が読経しました。協働センター代表の頼政さんより「被災された方々の中には、25年を経た今だからこそ話せる、“教訓”とは呼べないかもしれないが、大切な一人ひとりの小さな声がある。今後もその声を真摯に受け止め、支援活動を続けていきたい」とお話し頂きました。その後、特製のぜんざいとお茶で温まりながら、協働センターにゆかりのある方々ともに静かな時を過ごしました。
★新大池東住宅サロン
震災の日に発足した「阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク」が、被災した高齢者や障がい者の定期的な交流の場を提供しています。RSYでは毎年のように拠点を訪れており、久々の再会を喜びながら、住民の方々から現在の暮らしぶりや震災当時のお話を伺いました。
★サロンに参加された住民の声
・震災の時には家がつぶれて、その下敷きになった。ご近所さんが家の隙間から入り込んで、自分と家族を引っ張り出してくれた。以前からご近所さんとは、家族からもらった野菜をお裾分けするくらい仲良しだったから、そのおかげかもしれないね。「情けは人の為ならず」とはよく言ったもの。(70代・女性)
・ここ(サロン)にきて、子育ての悩みを聞いてもらっています。同じ年代やご近所には言えない話も、ここで聞いてもらえると心が安らぐんです。(40代・女性)
――――――――――――――――――――
施設見学
――――――――――――――――――――
★東遊園地
敷地内には、慰霊と復興のモニュメントが設置され、毎年1月17日には「阪神・淡路大震災1.17のつどい」が行われています。会場中心部に設けられた竹灯籠やモニュメント、当時の写真等をまとめた資料ブースを見学しました。
また関西地域で東日本大震災により福島県から避難された方々の支援を行っている、NPO法人全日本企業福祉協会(関西)の丸岡さんに、ツアーのお声がけをしたところ、福島県外避難者の方とともに東遊園地でお会いでき、追悼の志を共有しました。
★人と防災未来センター
こちらは震災の経験と教訓を後世に語り継ぎ、防災や減災の拠点として、役立つ情報が盛りだくさんです。センター内の資料室には、サロンでもお世話になった元阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク代表の故・黒田裕子さんのコーナーが期間限定で設置され、仮設住宅をはじめ支援記録の一部が公開されています。細かな心配りや哲学的な言葉が並ぶノートを見ていると、あっという間に時間が過ぎていきました。
――――――――――――――――――――
ツアー参加者のコメント
――――――――――――――――――――
― 新大池東住宅サロンの方々との交流 ―
・男性の参加が多数みえたのが、なんとも嬉しかった。元気に歩いている方が多く、「13階まですいすいだよねー」と話され、サロンの世話役の方々への感謝も話されていた。私も地元でサロン活動等の世話役を務めて8年、運営にも苦労している。この世話役の方々も同じような苦労があるのだろうと感じた。
・当時の報道をまとめた冊子をもとに「被災者の報道はきれいごとで、報道されないことが山ほどある。避難所のトイレもひどい状況で、掃除する人はごく一部。自分も含め、掃除を手伝うこともなかった」とお話いただいた。当時の状況や心境を考えれば、ご本人は悪くはないのに、今も心の奥深くでは、悩みや後悔として残っているのだと感じた。
・参加していた80代の女性は、歩行器を使っての歩行のため、一人での外出は難しいながらも、周囲のサポートを受け、欠かさず参加されている。「一人で部屋にいると話し相手も無いが、ここに来ると皆で話が出来るから楽しい。」と話されたのが印象的だった。何時までも仲良く暮らして欲しい。毎年ツアーに参加する中で、都市型災害の参考になるのはやはり神戸だと実感した。名古屋で災害ボランティアコーディネーターを目指す者として、今後も活動を続けていきたい。
― ツアーで得た学び ―
・また一年被災された皆さんの気持ちが積み重なる。多くの想いとは反対に25年という月日が人々の記憶を薄めていく。被災地NGO協働センターの追悼式から始まるこのツアーでは、自分が今年一年きちんと活動ができたのか、反省と気づきを確認する貴重な時間を頂いている。
・東遊園地の一角には、「隣の建造物に寄りかかって完全倒壊を辛うじて免れている家」の写真が展示され、「傾いている家のおばあちゃん。『私は50・60年生きてきたから、余震で潰れて死んでもいいねん』外に出ない。住み慣れた家で死にたい」という説明が添えられていた。写真を見て、私自身がこのような老人になってはいけないし、誰もがなってはいけないと思った。東日本大震災でも近所のお年寄りを説得して、亡くなる方がおられた。親切で、有能で、よい人たちの命が失われないような対策も地域防災活動の重要な一項目と改めて確認した。
・25年前の2月、とにかく現地を見ようと三宮に向かったが、公共交通機関は途中までしか走っておらず、徒歩で移動した。日常生活に戻ったように道路を走る自動車やバイクと、倒壊したビルとが共存する歪な風景は、今でもハッキリと覚えている。神戸との繋がりはなかったが、震災を機に、時間を見つけては通い続けてきた。大学時代の縁で今回参加でき、被災地に関わり続けてきたRSYの営みを感じた。栗田さんや愛ちゃんは、神戸で生きる人たちと共に寄り添ってきたのだなぁと。今後は、震災の日を一人で訪れ終わるのではなく、できる限り多くの人に会い、伝えていくことを自分なりに続けていきたい。
本ツアーの実施にご協力いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。












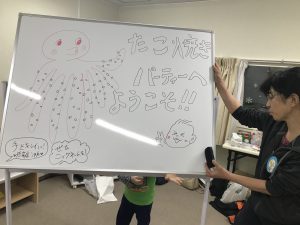








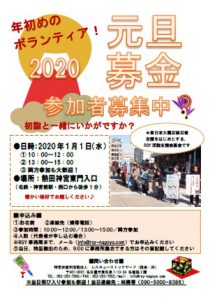

-212x300.jpg)