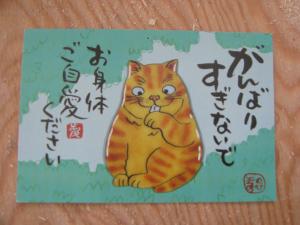みなさま
いつもお世話になっております。RSY事務局です。
この度、8月に行う東日本大震災復興応援企画「育もう!子どもたちの元気な笑顔を!」(仮)のボランティア募集を行います。これまで様々なかたちで 被災地支援に関わっていらっしゃる方はもちろん、何かしたいけどなかなかこれまで関われなかった方でも、以下の詳細をお読みいただき、目的や内容に賛同し ていただけるみなさんと、これから一緒に企画を作っていきたいと思っています。
8月までに月に1~2回の実行委員会を開催していく予定で、今回は第1回目の実行委員会のご案内をいたします。まずはぜひ実行委員会にご参加ください。
■第1回目の実行委員会
日時:5月17日(木)19:00~
場所:RSY事務所(名古屋市東区泉1-13-34 名建協2F)
★実行委員会に参加希望の方は、事務局までご連絡ください。
メール:info♯rsy-nagoya.com(♯を@に変えて)
———————-
・名前(ふりがな):
・携帯電話:
・メールアドレス:
———————-
■東日本大震災復興応援企画詳細
「育もう!子どもたちの元気な笑顔を!」~ミュージカル・朗読・歌を通じて(仮)
【目的】東日本大震災によって被災した子どもたちが逆境に負けず、失ったいのちの分までも生き生きと生きてもらいたいと願う有縁の支援者が集い、互いが元気な笑顔を育みあうことを目的とする。
【経緯】東日本大震災発生当初から、RSYはご縁のあった宮城県七ヶ浜町に拠点を設け今日まで支援活動を展開してきた。震災から8ヶ月の11月、同 町内の国際村ホールで、七ヶ浜町の子どもたちによる劇団「NaNa5931」が今回の震災を題材にしたミュージカルが上演された。鑑賞された町内外の被災 者らは涙に包まれ、大きな感動と明日への希望をもたらした。子どもたちが、今度はぜひお世話になった名古屋・全国の方々に披露し「ありがとう」を伝えたい と、初の県外公演に夢を膨らませている。一方で、愛知県に避難されてこられている県外避難者の方への支援拠点「愛知県被災者支援センター」や「東日本大震 災被災者支援センターなごや」を通じて、避難者有志にも現在の心境等を綴った思いを朗読していただき、その実態を広く県民に知らしめたい。
【日時】2012年8月11日(土)14:00開場・15:00開演~17:30
【場所】名古屋大学豊田講堂
【内容】ミュージカル、歌、朗読、展示、募金など
【主催】東日本大震災復興応援企画実行委員会(主管:NPO法人レスキューストックヤード)
【共催】名古屋大学減災連携研究センター
※NaNa5931のみなさんの行程は、8月9日の夜に名古屋に到着、12日の朝に名古屋発となり、途中、名古屋観光をしていただいたり、名古屋のみなさ んと交流の時間を設けたりしたいと思っています。そのスケジュールや内容についても、みなさんと一緒に考えていきたいと思っています。
以上、よろしくお願いいたします。

 今日の作業は16時に終了。
今日の作業は16時に終了。

 片 付けが終わった後は、今日のことを振り返りつつ反省会を子どもたちと行いました。「ホットケーキを食べるお皿の数、お客さんの座るイスの数が足りない。」 「ホットケーキのトッピングがもっとあったら良かった。」などお店の内容・効率についての話もでましたが、「出張試食があったからこれだけ人がきたと思 う。出張試食やって良かった」「美味しいっていろんな人から言われた。」「(イベントに)友達も来ていて、話してきた。そしたらホットケーキのところに来 てくれた。」など自分たちの役割についての感想、人と接することで知った情報を聞けたことが一番良かったです。
片 付けが終わった後は、今日のことを振り返りつつ反省会を子どもたちと行いました。「ホットケーキを食べるお皿の数、お客さんの座るイスの数が足りない。」 「ホットケーキのトッピングがもっとあったら良かった。」などお店の内容・効率についての話もでましたが、「出張試食があったからこれだけ人がきたと思 う。出張試食やって良かった」「美味しいっていろんな人から言われた。」「(イベントに)友達も来ていて、話してきた。そしたらホットケーキのところに来 てくれた。」など自分たちの役割についての感想、人と接することで知った情報を聞けたことが一番良かったです。