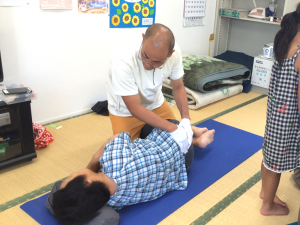皆様
お世話になります。RSY浦野です。
RSYでは震災がつなぐ全国ネットワークをはじめ、当団体と繋がりのある支援団体
の皆様と協働し、8月19日の大雨で甚大な被害を受けている兵庫県丹波市へ支援
活動を展開しております。
現在は、丹波市災害ボランティアセンターを拠点とし、震つな加盟メンバーのピース
ボート、被災地NGO協慟センター、丹波市災害ボランティアネットまごころさんらと共
に活動しています。
RSYからは、浦野・高木・松永、名古屋のボランティアさん1名が派遣されています。
===============================================
8月25日(月)~28日(水)兵庫県丹波市水害支援報告
===============================================
▼現在の動き
(ボラセンでの活動)
・丹波市災害ボランティアセンター前山サテライトにてボラセン運営サポートを実施
・主な活動はボランティアマッチングと被災地宅の個別訪問調査
・毎日400~500名程度のボランティアが現地で活動している
(地域での活動)
・前山地域の断水集落(徳尾・大杉・谷上・鴨阪・尾端)への炊き出し&ミニ喫茶の
実施
※炊き出し実施までの経緯
・全国曹洞宗青年会のAさんより、「特に女性から炊き出し希望の声が上がってい
る」と報告を受ける。
ボラセンの個別訪問や、地域の方に聞き取りをすると
「1週間働き続けてもう今は何もしたくない」「体がぐったり疲れて食事を用意するの
が大変」「コンビニやスーパーの惣菜も1週間続くと食べるのが辛くなる」「炊飯ぐら
いはできるけど台所が被害を受け自炊できない」「家は床板が外してあるし、空い
ている部屋も家財道具だらけなので落ち着ける場所がない」「1~2回御馳走になる
ぐらいなら親戚のお世話にもなれるが、度々は気兼ねして甘えられない」
など、「食」を切り口に、健康・安心できる環境・疲れの蓄積・遠慮や気兼ねなどに関
する課題が多数あることが分かった。そこで、協力団体に応援を求め、当面2週間
を目途に炊き出しプログラムを実施することとなった。
※概要(1回目)
・日時:8月29日(金)12時より配食開始~15時頃まで
・対象人数:上記集落の住民150名程度
・場所:ひなたぼっこカフェ
・内容:市に集められた救援物資の一部を会場にて配布。炊き出しと共に、ひなた
ぼっこカフェによる無料喫茶の実施
※協力団体
・宗福寺(曹洞宗/そうふくじ)
・神戸国際支縁機構
・全国曹洞宗青年会
・震災がつなぐ全国ネットワーク(RSY事務局)
※今後の予定(現在までの決定分・場所は未定)
・9月1日(月)曹洞宗ボランティア
・9月12日(金)神戸国際支縁機構
・9月16日(火)神戸国際支縁機構
▼個別訪問から見えてきた主な住民の声(課題)
〇作業に関わること
・床下の泥かきは目途が立ってきたが、乾燥→消毒→家財道具の収納などはこれ
から。あと1~2週間で畳が入ると過程すると、当面1ヶ月の間にもう一度作業の山場
を迎える。ただし業者混雑のため送れる可能性あり。その際のニーズキャッチとボ
ランティアの確保。
・ガラス、床、サッシ、食器あらいなど、何度やってもきれいにならない作業がこれか
ら待っている。家族でぼちぼち進めていくしかない。
・床下の処理のタイミングが分からない。どの程度乾燥させれば次の作業ができる
のか目視でチェックできる目安が欲しい。
・田畑に甚大な被害。農機具も全滅したという世帯も少なくない。国からの補助金は
あると思うが、今後の復旧をどのように進めていけばよいのか。
※「自分の家は十分やってもらったので、もっとひどい人を手伝ってあげて」という声
が増えてきた。また、細かい作業までボランティアに手伝ってもらってよいのか躊躇
されている方も少なくない。
〇生活に関わること
(食)炊き出しの経過報告の通り
(入浴)親戚の家で使わせてもらうも、度々借りるのは気が引ける。被災者に解放さ
れている入浴施設が5~6ヵ所あるが、どこがやっているのか分からない。(地域のボ
ランティアが知っていたため情報提供)
(洗濯)水が出るようになったが、まだ濁っているため洗濯には使えない。コインラン
ドリーを利用している。(気にせず使っている人もいる)
(寝床)家の2階を利用。しかし高齢の家族がいる場合は2階に上れないため施設
や兄弟、親戚の家で預かってもらっている。床下がほとんど開いたままの家でも何
とかスペースを確保し、寝起きしている方もいる。
(心・身体状況)
・『夜眠れない』という声多数。
・頭がボーっとして物忘れがひどくなった。
・持病があっても病院に行けていない。
・体のあちこち(腰と足)が痛い。次の雨が怖くて仕方がない。
・不安からか水から逃げる夢を見るようになった。
・この1週間はボランティアや親戚に手伝ってもらっていたので、気を遣う部分も多
かったが、久しぶりに家族だけの時間がとれてホッとした。(でもやることは山積)
・被害がひどかった地域のことを考えると、物資が欲しいと思っても遠慮して取り
にいけない。
上記の声から、今後はますます生活支援の必要性を感じます。先駆けて、被災地
NGO協慟センターと神戸足湯隊の学生たちが、避難所にて足湯ボランティアを開
始します。今後は炊き出しプログラムとも連動し、なるべく休息できたり、次のこと
をゆっくり考えたり、当時の様子や今の不安を安心して語れる場を提供していけ
ればと思います。
=============================================
お礼
=============================================
公益社団法人名古屋青年会議所様より、冷たいスポーツドリンク
約400本をご提供頂きました。
被災者宅への個別訪問や炊き出しの際に、お見舞い品としてお届
けし、とても喜ばれています。
温かいご支援に感謝致します。
=============================================
被災地支援活動募金にご協力ください!!
=============================================
以下の方法で募金・寄付を募集しております。
7月~8月にかけて発生した台風・大雨被害の被災地支援活動募金です。みなさ
まのお気持ちをRSYの活動を通じ届けさせていただきます。
〇街頭募金やります。活動に参加して下さる方募集!
・日時/2014年8月30日(土)13:00~17:00(途中参加・途中抜け可)
・場所/セントラルパーク地下街 インフォメーションスクエア
・集合/12:30にRSY事務所、または現地集合
・内容/今年の台風、集中豪雨での被災地支援活動募金
・連絡先/090-5000-8386(RSY林)
※屋内のため雨天決行です。
※大雨・洪水・暴風いずれかの警報が出ていたら中止とします。
==========================
〇寄付金は下記でも受け付けております。
<銀行振込>
三菱東京UFJ銀行 本山支店 普通3505681
特定非営利活動法人レスキューストックヤード
※お名前の前に「カツドウキフ」とご入力ください。
<郵便振替>
00800-3-126026
特定非営利活動法人レスキューストックヤード
※通信欄に「カツドウキフ」とご記入ください。
<クレジット>