みなさま
RSY事務局です。
3月8日(水)に開催した、2022年度の被災地支援に関する報告会が無事に終了しました。当日は、リアル&オンライン合わせて約40名の方が参加。2022年度にRSYが関わらせて頂いた、石川県小松市(9月~3月派遣)、静岡市清水区(10月~3月派遣)、佐賀県武雄市(年間5回派遣)の3か所での活動をリレートーク形式で繋ぎ、それぞれ参加したボランティアの方々から、活動の様子をお話頂きました。報告の中で見えてきた新たな課題もふまえ、RSYは今後も被災者支援を継続していきます。
以下、概要です。
1.RSY代表理事・栗田暢之挨拶
相次ぐ災害で本法人が現場に赴き、被災者の現状をお届けすることができているのは、日ごろ応援して下さる皆様のご支援の賜物であると深く感謝申し上げたい。
RSYは被災者支援において、「すぐにいく」「傍にいて丁寧に関わる」「ながく関わる」をモットーとしてきた。コロナ禍で「すぐにいく」ことは厳しくなったが、「丁寧に関わる」という点については従来の姿勢を継承してきた。しかし同時に、長い復興の中では、一部しか関われていないというジレンマも抱えている。
このような状況の中、阪神・淡路大震災からの支援仲間で、武雄市の(一社)おもやい代表・鈴木氏からは、「RSYから派遣されるボランティアの女性たちは、到着早々カバンを置いて「様子を見に行ってくる!」と被災者のもとに出かけていく。その姿はとてもパワフル。たまに来てくれる人だからこそ気づける変化があり、助かっている」という言葉も頂いている。皆様との協働のおかげでより「丁寧な関わり」が実現できているのではないかと思う。(武雄市は令和元年と3年に被災)
一方で、私達は、名古屋で災害が起こったらどうなるか?どうするか?という命題を突き付けられている。今回の報告会は、この点についても考えを深める機会にしたい。
今回の取り組みは、
RSY会員・関係団体・個人の皆様からのご寄付と共に、
日本財団「令和4年8月大雨被害に関わる支援活動」助成
日本財団「令和4年台風第15号被害に関わる支援活動」助成
![]()
生活協同組合連合会アイチョイス様
藤田医科大学様など
からの多大なるご協力のもと、実施することができた。深くお礼を申し上げたい。
2.2023年度・RSY被災者支援の概要(RSY常務理事・浦野)
今年度支援に関わった、石川県小松市・静岡県清水区・佐賀県武雄市では、特に情報が入りにくく、支援が届きにくい山間地や小地域において、避難生活で優先順位の高い「食の確保」と、災害関連死のリスクにさらされやすい「要配慮者ニーズの早期把握」、地元支援団体との「情報共有」、公的支援や水害後の家屋保全に関する分かりやすい「情報提供」、「孤立防止」、被災者の「エンパワーメント」の6つを活動の軸に据え、のべ約120名のボランティアを派遣することができた。また、2015年関東・東北豪雨水害以来、活躍中の「RSY看護チーム」も奮闘し、全ての被災地に1~3名の看護専門職に同行頂くことで、きめの細かいニーズ把握に繋がった。
RSYの生活支援プログラムで定番になりつつある、「あったかごはん食堂」(炊き出し支援の名称)には、碧南防災ボランティア連絡会と連携し、小松市で1,460食(12回)、清水区で260食(全4回)を提供することができた。これらをニーズキャッチのきっかけとしながら、要配慮者世帯の絞り込みと、地元の専門機関につなぐ役割を果たすことができたと思う。また、新たな顔ぶれとして、株式会社デンソー社員の皆様がボランティア休暇を使って参加して下さり大変助かった。
今回は、震つな加盟団体や、建築の専門的な知識のあるRSY団体会員の方々と連携し、微力ながら水害後の家屋保全作業のお手伝いもした。災害頻発と甚大化を前に、RSYもこれらの知識や技術を持つ人材の確保が新たな課題であると認識した。
いずれにしても、早期に様々な切り口を通じて、支援が必要な方を明確に特定することが、あらゆる支援を確実にひとりに繋げる突破口になることをひしひしと感じている。
3.リレートーク
①稲垣早海律さん(RSYボランティア)(小松市)
山間地域で、特に孤立が心配だった中ノ峠町の十数世帯の方々に、「あったかごはん食堂」の炊き出しをお届けする役割を担った。最初は警戒気味だった住民の方々も、足しげく通うにつれて次第に信頼関係を作ることができた。留守宅には手紙を入れて訪問したことを伝えると、手書きのお返事が置いてあったり、様々な形でコミュニケーションが深まることを実感した。この繋がりを通じて、世帯の生活状況が把握できたので、世帯構成&再建進捗リストにまとめ、RSYスタッフを通じ、社会福祉協議会等に報告してもらうことができた。できるだけ同じ人が通えるとよいが、それぞれの都合でボランティア側の顔ぶれが変わることも多いので、引継ぎ方の工夫は今後検討していきたい。
②藤井文香さん(RSY看護ボラ)(小松市)
看護師ボランティアとして、中海町を担当した。当初から住民の方々が主体的に公民館を「救護所」として機能させていたため、人・物・情報の提供が届きやすい環境があり関心した。公民館の一角に健康相談コーナーを設けたり、地域の方から心配な世帯をお聞きして個別訪問する中で、一人暮らしの高齢者や障がいのある方がいる世帯が、周囲に遠慮や気兼ねをして、支援が求められにくい状況があることを知った。その中で特に印象的だったのが、「私の被災は軽かったから公民館に物をもらいに行くのは申し訳ない」という言葉。我慢に我慢を重ね健康状態の悪化が心配されるケースもあった。看護ボラ同士でゆっくりお話を聞きながら、早めの受診や介護保険利用への仲介ができたことに、専門職としての役割を実感した。
③岡田雅美さん(名古屋みどり災害ボランティアネットワーク)(静岡市清水区)
今回お手伝いをした家屋は平屋で、床上20~30㎝の浸水被害があった。母子家庭で寝る場所がないので娘さんとネットカフェを転々とされていた。訪問すると、流し台の下やサッシは泥だらけ。母親は「3日間食欲がわかず食べ物が喉を通らない」と漏らしていたので、一緒にきれいにしようと励ました。「窓ガラスの泥の汚れがなかなか落ちない」という相談については、食器用洗剤を水で薄めた液を作るとよいこと、サッシのレールの細かい汚れは、歯ブラシできれいに取れるなどを伝えた。お隣さんからも「うちも見て欲しい」と声がかかり、近くでちょっとした質問に答えてくれる人がもっと必要だと感じた。また、「ミニ相談会(※)」では、最初雨が降っていて不機嫌そうに会場に来られた方が、帰り際はホットした表情を見せていた。相談会場での食事提供や足湯を通じて、「どうしてよいか分からない時に、分かりやすい説明をしてもらって本当に助かった」という声を多く聞かせて頂いた。
※ミニ相談会:「今後の生活再建に関する無料ミニ相談会」の略。法律や災害後の家屋保全の専門家をお迎えし、公的支援制度やカビ、寒さ対策等についてレクチャー頂いている。また、災害VCや市の担当者も同席し、ボランティアや応急修理制度、生活必需品等の申し込みをその場で出来るワンストップ型支援の場を提供した。会場には、足湯やお食事&カフェコーナーも設置して、心に溜めていた不安や疲れを吐き出し、リラックスして頂けるよう配慮した。RSYは企画・運営を担当。
④伊東ゆかりさん(なごや防災ボラネット)(静岡市清水区)
「ミニ相談会」の会場の一つとなった、清水区の柏尾自治会は、自治会独自で床上・床下浸水を色分けし情報整理をしていた。中には1m以上浸水していた箇所もあり、大変な状況だった。相談会のチラシをお届けしに個別訪問を行ったところ、3人暮らしの世帯と遭遇。水害当時、娘と自分は2階に避難するも妻は介護が必要だったため今は施設に預けているという。相談会にお誘いするも強く遠慮されたが、気になったので翌日再訪問した。すると、庭の泥を娘さんが一人で片づけていたので手伝わせて頂いた。娘さんは「これでとても気が楽になった」と明るい笑顔を見せてくれたので、再度相談会へお誘いした。別の方からは「過去の水害経験からかさ上げしたところに浸水。なかなか買い物にも行けないので缶詰で食べしのいでいた」というお話も聞いた。相談会場での食事提供の際、「私たちなんかもらっていいの?」などの声もあったが、「家族分どうぞ」というと「久しぶりにおいしいものが食べられる」ととても喜んで下さった。今回の活動で個別訪問の重要性が理解できた。最初は、「うちは大丈夫です」とおっしゃっていた方も、翌日再び訪れると大丈夫ではないことが多くあった。一人ひとりのペースに合わせて関わることがいかに大切かを実感した。
⑤加藤都さん(名古屋みなみ災害ボランティアネットワーク)(武雄市)
令和元年・3年と続けて通い続けている。私達の活動窓口としてお世話になっているのが、おもやいさん。武雄に到着するとまずはここに顔をだしてから、住民の方のお宅に伺う。住民の中には、連日の片づけで急に体調を崩す方もいらっしゃったので、看護チームとして対処させて頂いた。毎日顔を出すことで信頼関係ができ、その方の人となりも良く分かってきた。自らも被災しているのに、周囲に気を配りすぎるがあまり気持ちの浮き沈みに悩むEさん、水害後の苛立ちから、他者からの支援をなかなか受け入れられないKさんなどには、「この方が本当に望んでいることは何か」を常に考え、心の内を安心して吐き出せるような関わり方を心掛けた。西九州大学の学生チームとRSYが、復興期の孤立防止と食を通じた健康維持と活力向上を目的に、ご自宅訪問型の「あったかごはん食堂」を開催した。我が家という安心できる場所で調理をしながら学生と楽しく交流したり、写真係や調理係など、それぞれが役割を持ち、ご本人と一緒に場を作ることで、みるみる元気になっていく様子がうかがえた。年に何度か行き来する関係にも、長い生活再建の一部を支える意味があることを実感した。
⑥椿佳代さん(RSYボランティア)(武雄市)
「NPO法人みつわ」のある久津具地区は、水害時に地区の9割が被災。みつわは、在宅避難者の支援拠点として活動していた。RSYは、令和3年から拠点運営を手伝うと共に、2019年台風19号水害で被災した長野市豊野区との交流企画に関わるなどしていた。令和4年2月~3月はコロナ蔓延期で直接現地入りできなかったので、節分や花見の季節にちなんだご当地名古屋のプレゼントお届けして交流を続けた。次の災害に向けた防災プログラムを実施したいという代表の希望を受け、コロナが下火になったと同時に、5月には手作り防災頭巾、7月・10月にはポリ袋で作る非常食「パッククッキング」のワークショップを開催。地区のオリジナルメニューも誕生した。参加者からは「パッククッキングは知っていたけど、いざという時うまく調理できなかった。今回練習できてよかった!」と嬉しいコメントも頂いた。また、みつわと地元の民生委員のコラボで誕生したのが「個人ボックス」。避難後にあったらよかったものを厳選してBOXに入れ、避難先の公民館やみつわに常時置けるよう準備を進めている。地元NPOと一緒に取り組む、考えることで、住民のエンパワーメントを支援していくことがとても重要だと感じた。
4.問題提起(RSY代表理事・栗田暢之)
台風15号で被災した静岡市のケースは、超高齢化社会、地域の希薄化、格差社会などを背景に、自ら助けを求められない、誰に相談すればよいかわからないという現代社会の病に、さらに災害が拍車をかけていく状況が見えた。清水区ではスタッフが、多頭飼育、障がい高齢者の兄弟、母子家庭の深刻なニーズを見つけた。この事例については、緊急性が高かったこともあり、静岡県の危機情報課課長へ報告、その後市の危機管理課に伝達され、保健師を中心に後追い訪問を行ったという報告を受けた。しかし、この事例は氷山の一角とも考えられ、12000世帯の被災に対し、同様に取り残されている方がいないかを早急に確認すべきと伝えた。
その後も県は、市町村に災害ケースマネジメントや、アセスメント調査実施について通知をだしたが、財源、対象者、支援内容を丁寧に説明し伴走する人がいなければ、市単独での対応が難しいようだった。一方で、静岡県弁護士会には、被災者の多くが車中泊やネットカフェで過ごしており、「今日ねる場所」がなく途方に暮れているという切実な相談が寄せられていた。避難所が早々に閉所したことにより、寝床や食事の提供ルートが絶たれたことも原因となっている。
市には、静岡の災害は内水氾濫で「状況が見えにくい被害」ではあるが、個人情報を持っているのは行政。これらの名簿をもとに被災地域を突合し、統一の調査票で個別訪問し、統括する部局が情報をまとめることができるとよいと提案した。その後ほどなくして、市内一斉の個別訪問調査が実施された。しかし、市の関係課が集まる場で、NPOや災害VC等が持っている情報を共有する場の必要性を打診するも統括課が決まらず、実現には至らなかった。
これらの結果から、日常から行政、社協、NPO等と3者連携体制の構築が必須であり、まさに、愛知・名古屋は大丈夫か?と問われていると感じた。RSYとしてもこの課題と真剣に向き合い、皆様と共に取り組みを進めていきたい。
5.バズセッション
皆さんの発表をふまえ、参加者同士で活発な意見交換を行いました。
6.被災地からのメッセージ
★本清美さん(小松市中海町住民)
昨年8月の豪雨以来レスキューストックヤードの皆さんをはじめ、たくさんのボランティアの方々にご尽力頂き、感謝しかありません。なんとか元の生活に戻りつつあります。町内に留まる方、また、去る方と色々な方がいます。今は、少し寂しいです。まだまだ、市、県、国の対応も色々ですが、もっとこれからも住みやすい町内に整備してほしいです。私も、全力でお手伝いさせていただきます。皆さんには、お願いしか出来ません。これからもよろしくお願いします。
★森川昇御さん(清水区天王町自治会会長)
水害が起こった時に、自家用車が全て被災したため、地域の安否確認や関係機関への連絡などが滞り、本当に苦労しました。私の他にも、罹災証明書や各種手続、区役所で弁護士さんの相談会などがあっても、行けずに途方に暮れていた地域の方々も多かったと思います。特に賃貸住宅の人達が、家の修繕や応急修理制度の活用をどのように行ったらよいか分からず困っているのではないかと感じていたため、私たちの地域で「今後の生活再建に関する無料ミニ相談会」を開催して頂きました。相談会というと敷居が高くなるところを、お弁当やおいしい珈琲の提供、足湯などで場を和ませてもらい、久しぶりにゆっくりお話ができた方もいたと思います。地域は大分落ち着きましたが、次の災害に備えて防災対策にはしっかりと取り組んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。
★荒川千代美さん(NPO法人みつわ代表)
私は、介護施設の運営をしながらNPOの活動もさせて頂いています。令和元年、令和3年と相次ぐ水害の被害を目の当たりにした時、こんなに大変な地域だったという驚きと、何をしてあげれば良いのか途方に暮れている時に、いち早く駆けつけてくださったのがRSYの方々でした。あらゆる所に、心と物資を運んでくださり、テレビでしか見たことのなかった、災害ボランティアの方々の無償の愛を沢山頂きました。この事で、地域の方々との繋がりを強くして頂いたのも皆さんのお陰です。「悲しみは共有して小さく。逆に喜びは共有して大きく。手を携えて前に進む」という教訓を、RSY の方々から教えて頂きました。お陰様で、災害は不幸な事でしたかも知れませんが、より地域との心の結びつきを強くするためのきっかけになったと思います。ありがとうございました。これからも、アドバイスをよろしくお願い申し上げます。
★鈴木隆太さん(一般社団法人おもやい代表)
令和元年、3年と2度にわたる豪雨災害により被災をした佐賀県武雄市へ、たくさんのご支援をくださり本当にありがとうございました。RSYのスタッフの皆様、また看護専門の方や、さらにはこれまでRSYの活動を共にされて来られたボランティアの方々のパワーとお心遣いにはスタッフ一同、本当に感謝しております。被災された方々と向き合われる姿勢は、RSYがこれまで関わってこられた被災地での取り組みから積み重ねてこられたものであると同時に、またRSYの信念を強く感じます。そうした信念のもと、愛知県内の多くの方々と連携をしっかりと作られているその姿は私たちも学ばなければいけない、多くのことを教えてくださっております。短い期間に二度被災をしたことから、毎年春が来ると「今年の雨は大丈夫か」と、会う人会う人異口同音に言葉にされております。これからのこの地域における安心を作り上げていく仲間として、これからもどうぞよろしくお願いいたします!












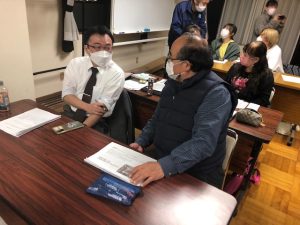


















-213x300.jpg)
-2-215x300.jpg)






















