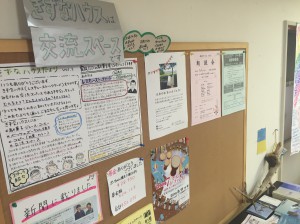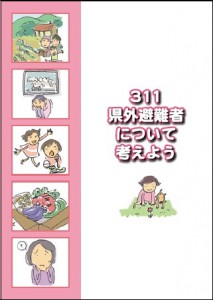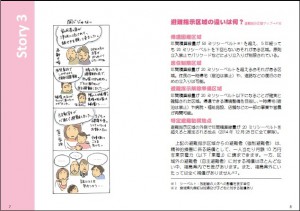みなさま
平成28年熊本地震において、RSYでは御船町を中心に活動を継続しています。
また、全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD準備会)では、熊本県内で活動するNPO団体と県、国らと共に頻繁に情報交換を行い、県内避難所の実態調査や環境改善、その他、支援の過不足を補い合うべく活動しています。以下、現地スタッフからの報告です。
———————————————————————————
▼LUSHジャパンからスキンケアセットが届きました(報告:浦野)
———————————————————————————
かねてからRSYの活動を応援してくださっているLUSHジャパンさんより、化粧水・保湿クリーム・リップクリーム・ドライシャンプー・ハンドクリームのスキンケアセット500セットが届きました。御船町の女性を中心に、避難所や役場・社協職員の皆さまにお渡ししています。天然素材・やさしい香りの商品に、手渡しすると表情が輝き、「避難所は乾燥しているので、こういうのが助かります」「とても香り!明日はつるつるになって女を取り戻すよ」「物資を運んだり炊き出し手伝ったりで手がガサガサ。いつも使ってるからとてもうれしい」など、大好評でした。今週末は、スタッフの方がハンドマッサージボランティアとして御船町に来てくださいます。主に、避難所や断水集落、車中泊の方用のテント村などで活動して頂く予定です。
——————————————————————————-
▼御船町田代東部集落への支援(報告:中西)
——————————————————————————-
避難所が町場から離れており、断水家屋や一部損壊被害の多い田代東部地区で、継続的な食事・生活支援を行っています。5月16日は名古屋からのボランティアチーム9名が、おいしい「なごや飯」をふるまって下さいました。この集落では、瓦屋根が落ちたお宅の雨漏り対策として、住民が協力してブルーシート張りを行っています。風でシートが舞わないよう、土嚢袋づくりを住民で行っていますが、高齢者が多いため重労働。そこで、名古屋のボランティアさんにお手伝いして頂きました。一緒に食事をしたり、作業をすると様々な心の内が語られます。RSY職能ボランティアで看護師の神田さんも、住民の方々の血圧を測りつつ、近況について健康状態や片付けの進捗状況などの聞き取りを行って下さいました。
【住民の声】
・母親と二人暮らし。地震の1年前ぐらいから母親は入退院を繰り返してる。今は市内の病院に入院中。食事が困るので毎日ここ(公民館)に取りに来てる。カップ麺とパンしかないけど。もう飽きたけど仕方ない。今日も取りに来た。今日はラッキーだった。みそかつ食べたことないって言ったら作ってくれて。うまかった。ごちそうさん。(50代男性)
・うちはバス停の分岐から山都に行く道の方。奥の方の家はみんな大丈夫だったけど手前の方の入り口の家はみんなやられた(被害にあった)。瓦も落ちたけん、高所恐怖症なのに屋根にのぼってブルーシートかけたたい。素人仕事だから雨が続くと心配。明日は部落のおまつり(小さな催し)があって、さっきまで町に買い出しにいっとったんよ。ほんとなら8月の祭りの打ち合わせも今ぐらいにしとるはずなんだけど今年はたぶんできないだろうな。役場に金がないじゃろうけん。(60代男性)
・バス停のとこに店があるでしょ?あの店ばあちゃんが膝悪くして腰も悪くしてから閉めたと。息子がいるとやけん、いろいろあってね。店がなくなってみんな困ってたから部落の婦人部の「ばぁばの会」で小さな店をやることにしたの。そのオープンが4月14日。ようやくオープンしたと思ったのに、店どころじゃなくなったとたい。ようやく少し落ち着いてきたから、午前と午後の店番を当番決めて2、3日前から開けられるようになったたい。近くにきたら寄ってね(60代女性)
・熊本の名物は、スイカ、メロン、デコポン、晩柑、トマト、辛子蓮根、馬刺し…。たくさんあるけん、遠いとこからきてくんなさったんじゃから、うまいもん食べて帰ってね(70代男性)
・ここらへんの人はみんながんばっとるよ。頑張る人が多い。60代でも「若い人」って言われるけんね、まだまだがんばらな。(60代男性)
・一緒につくりたっかたなぁ。残念だなぁ(時間が合わず今回は断念)(80代男性)
・おいしかったです。みんな。遠くから御船に来てくれてありがとうございます(60代女性)
・いま、家の墓見てきた。ひどいよ。墓石も骨壺もなんもぐちゃぐちゃ。どもならんばい(60代男性)
・この前まで私が土嚢作って置いたんだけど、一気になくなってね。悪いね、こんなことやってもらって。助かります。やってもらってみんなには悪いんだけどこれ(土嚢ぶくろ)を使う機会がないことを願ってるんだよね、いつも(60代男性)
・ちょっとこっちへ来てごらん。いいもの見せてあげるよ。これは作家もの。これは江戸時代の着物で作ったお雛様なんだよ。こんな小さなものが好きでね。50年買って集めて飾ってた。それがみんな倒れて。壊れて。割れて。掃除する気もおきなくて、ほら、割れた皿もそのまんま。熊本の陶芸作家さんの作品だったのにね。みんないい作品だったんだよ(80代女性)
・音楽家なんです。フルートをやってます。地震があってね、私達音楽家はみんな仕事がなくなちゃった。ホール専門に演奏してた人は演奏するホールがなくなっちゃって。あっても避難所になってたりして。演奏する場がなくなっちゃった。市内とか市内に近いところにそうした音楽家がたくさんいるんだけど、それなら避難所をみんなで分担して回って、演奏して元気づけようか、という話になって。今晩市内で集まりがあるんですけど100人ぐらいさんかするみたいなんです。音楽で何ができるかわからないけど少しでも癒しになってもらえたらと思ってるんです(50代女性)
・嫁さんが町に家建てたもんでそこで暮らしてます。昼間は少しでも片付けようとじいさんとこっちに来てる。じいさんは4月14日の地震の後、トラックと塀の間に挟まる事故にあって、手術して退院したばかりとたい。じゃけんあまり使ったらいかんけど車がないと不便で不便で。バスは朝と昼でしょ。帰りは17時しかないし。とてもとてもバスはよう使わん。じいさんは耳が遠いけん話ばしよると聞こえんばいイライラする。私も腰まがっとるばい大きいもんもてんが割れたガラスやなんか掃除しとると。大きかゴミはどうすればよかと?道路まで出すのもしんどい。屋根にブルーシートばかけてほしいって区長さんにお願いしたとたばってん、うちは2階があるけん素人じゃ無理だって。若い人は町に住んでるからもう2階はいらないし、片づけが終わったら2階を取ってもらって平屋にしてじいさんと二人じゃけん充分。16日の時はじいさんが入院しとって、私一人この家におって、上から瓦は落ちてくるし、石は倒れるし本当にこわかったたい(80代女性)
・日にね、何度も見に来よるよ。今は2軒先のあの店に暮らしとる。前は店をやっとった。2間ぐらいあるとやけん、食べて寝てするには困らん。(自宅の)瓦が全部落ちてしまったから、中が濡れてしもうて。布団やこたつ布団なんかは出しとったんやけど服なんかはもうだめたい。捨てなあかんやろ。私もほれ、こうして(杖)足が悪いけんね、ずいぶん前に手術して両方のひざに金属入っとるとよ、じゃけんよう運べんの。せめて屋根にブルーシートだけでもはっとったらと思って区長さんにも大工さんにもお願いしたんだけど。息子も仕事で忙しくてだめ。このままだとせっかく残った家財道具がみんなずぶぬれになってしまう。なんとかしてもらえないやろうか。ほら、あの窓から後ろの石垣が見えると?あの石垣はもっとずっと奥にあったとたい。それが地震で窓ガラスば割るほど近づいてきよった。こっち(別の)の石垣がうちに倒れてきたときは「ドーン」ってすごい音がして家が壊れたかとびっくりして心臓が止まりそうだったとよ。ほら、うちン中も水がはいっとるやろ、昨日の雨で雨漏りして。瓦がないから。ブルーシートだれかかけてくれんとかね(70代女性)
・うちに帰ったばたんきゅーで。夫婦の会話なんて地震が起こってからなくなっちゃった。ろくな会話してない。もううちに帰るとへとへとすぎて。ご飯食べてお風呂入ったら、もう何もできなくて布団に入って。そうして毎日がものすごいスピードですぎていくとよ(50代女性)
・田植えができんちゅうてみんな今年はどぎゃんするとって頭かかえとるよ(60代男性)
・炊き出し、って言っても、避難所じゃない人たち(在宅)は、なかなか来ないんだよね。なんか施し受けとるみたいな感じがするけんね。集まってわいわい食べてもらいたいだけなんだけど(40代女性)
・うちも甲佐で被災した。仕事してるから片付けたいんだけど全然できない。全然。地震のときのまま。いまは弟のうちで生活してる(50代女性)
・ゴミを片付けたいんだけど、気力がわかない。2階から荷物を下ろすのも大変。じいちゃんは腹きって(手術して)日が浅いけん、運転させられないからバスで来て日中かたつけしとる。(80代女性)
・バスで町まで買い物にでるけど、黒潮市場もマインも空いとらんけん、買い物に不自由しとる。あそこが一番バス停に近いけん。帰りに荷物を持ってくるのがきつか(60代男性)
・こんな馬鹿話でもして笑ってなきゃ、やってられやせんけん。みんなで馬鹿話しとる。 年寄りも結構好きで話に入ってきて盛り上がるよ(60代女性)
・ボランティアってったって、こんなところまで来てくれてありがたいし頭が下がるよ。空港までタクシーに乗って帰るって。そんなとこまで金つかわせらんねえよ。それぐらい俺がしてやる。わざわざ遠くまできてくれて、それぐらいしないとばちがあたるよ。あんたいつ帰るの。帰るときは俺に言えよ(60代男性)
———————————————————————————————————
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)の動き(報告:松永)
———————————————————————————————————
が開催する「熊本地震・支援団体火の国会議(略:火の国会議)」の事務局として活動。毎日19時より県庁(県青年会館から会場変更)にて火の国会議を実施し、県内外の支援団体が集まり情報共有を行っています。現在までに約180団体が参加しています。また、RSY松永はJVOADの熊本市のエリアコーディネーターとして活動しています。現在の状況は以下の通り。
〇災害VCについて
・熊本市災害ボランティアセンターでは、5月17日現在で1700件弱のニーズが残っている。しかし、交通状態や運営者の不足、また自宅の片づけ等も入れる人数が限られている等の理由から、平日500名、休日1000名程度の受け入れを行っている。水害対応の人海戦術とは異なり、息の長い支援が必要とされている。
・主な活動内容は、割れた瓦やブロック塀の片づけ、自宅内の清掃、避難所での活動(清掃等)等。
・瓦が落ちたお宅の屋根へのブルーシート張りのニーズは多くあるが、高所作業となり資格や経験が必要で、市町村の災害VCでは対応できない。そのため、NPO等で専門家(大工等)を呼び対応しているケースもある。
〇炊き出しについて
・益城町では炊き出し調整をNPOへ依頼され、地元のNPOくまもとが益城町での炊き出し調整を行っている(http://www.npokumamoto.com/takidashi.html)
・長期化する避難生活で、野菜等の栄養バランスが取れた炊き出しニーズが高いが、熊本県内は5月に入り、日中の気温は30度近くになる日も多く、厚労省等から炊き出しで衛生面への注意喚起がなされている。
〇避難所について
・県内の避難所は、GW後の学校再開に伴う統廃合後は大きな動きは出ていない。余震も続いていて、夜は避難所生活という方もまだまだいる。
・熊本市内の拠点避難所を巡回する中で、避難所内でテレビをずっと見ている方、なにもすることがなく掲示板やチラシ等を眺めている方が多い。生活のメリハリをつけるため、掃除の時間や体操の時間等をつくり生活リズムを整えることが必要とされている。
・熊本市では、避難所運営に避難者が関わってもらう自主運営に向けた取り組みが必要とされている中、日中避難所に残るのは高齢者ばかりで難しいとの声も出ている。しかし、食事の配給や避難所内の清掃など一部の運営の手伝いを少しでもしてもらえるような働きかけを外部支援者で行っていく必要がある。
・夏季に向けて、暑さや熱中症対策が必要とされていて、行政が避難所へ扇風機等の準備を進めている。
〇仮設住宅について
・県内の被災11市町村で仮設住宅建設が着手され、現在で約1,800戸が建設予定。早ければ6月中旬に完成予定。一方で、市町村によっては建設用地の交渉が進んでいないところもあり、建設戸数はまだ増える見込み。また熊本市では応急仮設住宅が建設予定であるが、基本的には民間アパート等を利用したみなし仮設住宅の対応となる。
—————————————————————————–
▼RSYの活動が以下に紹介されました
—————————————————————————–
◆ジャーナリスト・江川昭子さん手記
「進化する民の力(上)」
「進化する民の力(下)」
——————————————————————
▼スタッフ・RSYボランティアの活動状況
—————————————————————-
・浦野(御船町支援・県内避難所改善)/4月20日~5月8日、5月13日~
・松永(JVOAD準備会事務局支援)/4月20日~
・中西(御船町支援)/4月20日~5月9日、5月13日~
・松山(震つな)/5月19日~20日
※栗田は週に2日間のペースで熊本入り。国・県・市町村との調整、JVOAD準備会事務局全体総括など
★JVOAD準備会・県内避難所改善チーム(RSY職能ボランティアチーム)
・神田夏美さん(看護師)/5月14日~17日
▼活動支援金募集
————————————————————
皆さまからお寄せ頂いた活動支援金は、主に被災地での生活支援プログラムに関わる企画・運営などに使わせて頂きます。(炊き出し・足湯ボランティア・サロン・生活物資提供・集落支援など)
<クレジットカード決済>
URLよりお願いいたします。
https://kessai.canpan.info/org/rsy/donation/
「都度寄付」よりお申し込み下さい。
<銀行振込>
三菱東京UFJ銀行 本山支店 普通3505681
特定非営利活動法人レスキューストックヤード
※お名前の前に「カツドウキフ」とご入力ください。
<郵便振替>
00800-3-126026
特定非営利活動法人レスキューストックヤード
※通信欄に「カツドウキフ」とご記入ください。